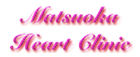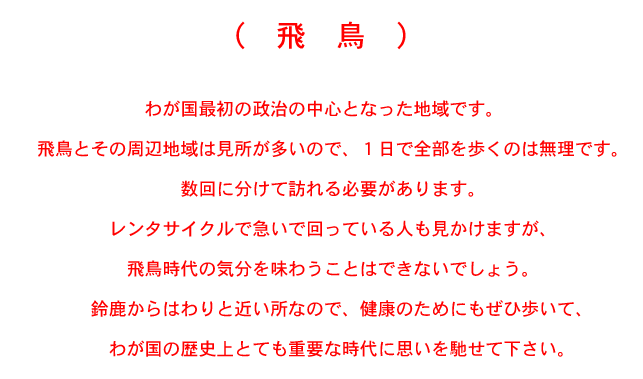(飛鳥寺)
蘇我馬子により596年に完成。周囲の風景もそうですが、妙に気持ちが落ち着く寺院です。日本最古の仏像である飛鳥大仏を安置。このような大切な仏像が触れるほど近くで見れ、写真撮影自由というのが驚きです。凛々しいお顔の男性的な仏像です。
ダイナミックに政治が動いた時代。日本という国を考えるならば、一度は必ず訪れるべきです。たった1400年ほど前のことです。

(石舞台)
蘇我馬子の墓と考えられている古墳です。これも自由に中に入れますし、修学旅行らしい子供たちは勝手に岩の上に上ったりしていました。
蘇我馬子は626年にこの世を去りました。仏教を日本に受け入れようとして、反対派の物部氏と対立し、587年に物部守屋を滅ぼしました。そして姪の子の聖徳太子を推古天皇の摂政とし、二人で日本を大胆に改革。607年には小野妹子を遣隋使として派遣しました。

(蘇我入鹿首塚と甘樫丘)
645年6月12日、馬子の孫の蘇我入鹿は中大兄皇子と中臣鎌足に裏切られ、皇極天皇の目前で刺殺されました。翌日、父親の蝦夷は甘樫丘の自宅に火を放って自害しました。大化の改新の始まりです。首塚は飛鳥寺のすぐ裏手にあります。
中臣鎌足の子孫である藤原氏が力を持っていた頃に書かれた日本書紀には蘇我氏が悪者扱いされていますが、最近の研究では、逆の見方も多いようです。

(甘樫丘から見た畝傍山)
甘樫丘から西側(飛鳥寺&蘇我入鹿首塚と反対方向)には、大和三山の一つ、畝傍山(うねびやま、199m)が見えます。本当に甘樫丘のロケーションは最高です。ここに居を構えた蘇我氏は真の実力者だったろうと思います。
写真の頂上展望台やふもとの広場ではたくさんの人々がくつろいでいました。

(甘樫丘から見た耳成山と天香久山)
甘樫丘(あまかしのおか、148m)から北側を見ると耳成山(みみなしやま、140m、写真左奥)と天香久山(あめのかぐやま、152m、右中央)が見えます。つまり、甘樫丘は大和三山の耳成山よりも高く、天香久山ともほぼ同じ高さなのです。にもかかわらず四山と言わず大和三山と言うのは、蘇我氏が甘樫丘から見て名付けたものだからではないのでしょうか。

(藤原宮跡と畝傍山)
694年、持統天皇は飛鳥から藤原京に遷都しました。甘樫丘をはさんで飛鳥宮とは反対側で、大和三山に囲まれた平坦な地域です。その後に続く平城京や平安京をしのぐ規模の、わが国初の本格的な都です。その中心にあった藤原宮跡が写真右側の木々の中にあります。この地から眺める大和三山は、不思議なくらい懐かしい風景に感じられました。

(亀石)
さて、飛鳥を歩くと狭い地域ながら色々変わったものに遭遇します。特にこの亀石はいつ、何の目的で作られたのか未だ不明な石造物ですが、かなり目立ちます。高さは約2mで、他には見かけない大胆なカットとデザインで、この顔を忘れることはなさそうです。甘樫丘の真南に位置し、高松塚古墳やキトラ古墳の方角を向いています。

(猿石)
亀石から南西に鬼の俎などいろいろ見ながらここまでゆっくりと歩いてくると、さすがに結構歩いたな~という感じです。周囲にゆったりと水を湛えた前方後円墳の欽明天皇陵の隣に吉備姫王墓がありますが、その門の中に猿石があります。正面から見ると4体(写真の左に最も猿らしいもう1体)あります。これらも亀石同様に独特な石像です。周遊路の帰り道には天武天皇・持統天皇陵(夫婦の古墳)があります。