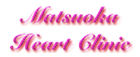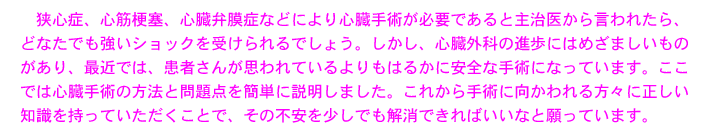( 特殊性 )
心臓手術と他の手術とはどこが違うのでしょうか? 一言でいうと、手術中にその臓器の機能を停止させなければならないことです。肺も胃腸も脳も肝臓も腎臓も骨も手術をうけている間でもしっかりと働いています。しかし、もし拍動している心臓を切開すれば血液が噴出して大出血となり、また切開部から空気が入って血管内に流れ、各臓器は空気が詰まって壊死してしまうでしょう。したがって、心臓を切開して内腔を手術する開心術では、心臓を停止させる必要があるのです。
しかし心臓を停止させるとなると、2つの大きな問題に直面します。
第1の問題点は、手術のあいだ心臓に代わって各臓器に血液を送り続ける方法が必要となることです。この方法を体外循環といい、人工心肺という機械を用いて心臓の代わりをします。
第2の問題点は停止させた心臓も血液が流れなければ壊死してしまうので、手術の間どうやって生かしておくかということです。しかし、血液を流せば心臓が動いてしまうので、血液を流さずに心臓を保護する方法が必要になります。この方法を心筋保護法といいます。
これらは従来より心臓外科の大きなテーマとなっています。なぜなら、これらの方法が完全であれば、手術には時間的制約がなくなり、何時間もかけてゆっくりと手術できるからです。しかし、現状では手術時間が長くなればなるほど、術後の状態は不良となります。そこで理想の体外循環と心筋保護法をめざして、日々研究が続けられているのです。したがって現在のところ、安全に手術を終えるためには、心臓を停止させる時間と体外循環を行う時間が少しでも短くなるように工夫することが重要なのです。
( 体外循環 )
人工心肺の操作は、体外循環専門の技師や心臓外科を志した若手医師が行います。ポイントは自分が心臓になったつもりで機械を操作することで、脳・肝臓・腎臓などの主要臓器へ血液を送る気持ちを持って優しくゆっくりとダイヤルを回します。人工心肺装置は思い通りの流量で血液を循環させることができますが、その他にも、血液に酸素や薬剤を加えたり、血液の温度調節を簡単に行えます。
実際には身体から心臓に還ってくる汚れた血液をチューブを用いて大静脈から装置に引き込み、人工肺の中で血液中の赤血球に酸素を結合させ、温度を調節してから、ポンプによって大動脈に送り込みます。これにより、心臓と肺を通らない血液循環の輪が完成します。
しかし、血液は本来の血管の中を流れるようにできているため、ビニールチューブや人工心肺装置の中などの人工物に接すると様々な反応を起こし、これが生体に戻って血管にダメージを与えてしまいます。その結果、心臓手術の術後には全身に浮腫が現れます。それは体外循環時間が長くなればなるほど強く現れ、術後の回復に大きく影響します。術後管理は若手医師の重要な勉強の場となりますが、全身の浮腫が軽減し、臓器の機能が回復してきたときにようやく安心して休むことができるのです。
( 心筋保護法 )
最近ではテレビで、心臓移植のためにドナーから提供された心臓がクーラーボックスで運ばれてゆくのを見ることがありますが、これこそがまさしく心筋保護法によるものです。
基本的には、冠状動脈へ高カリウム液を注入して心臓の動きを止め、その周囲に氷水を入れて心臓を冷却します。これにも時間的制約があり、現状では6時間以内が安全圏です。そのため心臓移植では急いで飛行機で運搬しているのですが、幸いにも狭い日本では6時間あれば全国どこへでも運搬して移植可能です。
心臓移植の場合には、心筋保護を行うのがドナー(提供者)の健康な心臓であるため、このような長時間の輸送が可能なのですが、普段の手術で扱う心臓は、広範囲の心筋梗塞であったり、長年にわたる弁膜症で心不全をおこしていたりするため、心筋保護もはるかに難しくなります。
さて、手術が終わり、いざ冠状動脈に血液を流して心臓の鼓動の再開を待ちますが、再び動き出した心臓の動きを見ればその手術の心筋保護が良かったかどうかがわかります。心臓を止めた時間が30分以内で短かければ、心筋保護の善し悪しにかかわらず大抵元気に心臓は動き出します。しかし、2時間以上の長時間にわたって心臓を止めた場合には、術中の心筋保護がうまくいったかどうかが、術後の心機能の回復の鍵を握ります。長時間にわたる心停止を必要とした場合には、術後管理で多かれ少なかれ強心剤の投与が必要になります。このように、現状では心停止時間が長くなれば心臓の機能が低下してしまうので、心臓を停める時間を短くするために熟練の手術テクニックが必要となるのです。
( 手術方法 )
心臓手術の対象となる疾患は主に3つに分けられます。
第1は先天性心疾患で、生まれながらにして心臓の構造に異常があるものです。一般的なものは、いわゆる心臓の壁に穴があいているというもので、具体的には、心臓の内腔を左右に分けている隔壁(中隔といいます)に欠損があるものです。心房中隔欠損症、心室中隔欠損症といわれる疾患であり、欠損孔に布を縫いつけてふさぎます。その他、血管が細すぎたり欠損しているものには人工的に血管を形成します。複雑な心奇形ほど生後早い時期に手術をする必要がありますが、あまりにも高度の奇形で修復が困難な場合には心臓移植の対象となります。
第2は弁膜症です。心臓内には4つの弁がありますが、手術の対象となるのは主に左側にある2つの弁、僧帽弁と大動脈弁です。これらが開きにくくなったものを狭窄症と呼び、反対にしっかりと閉じなくなって血液が逆流するものを閉鎖不全症と呼びます。弁膜症の手術では、まず自分の弁が残せるように弁形成術が考慮されますが、変形が高度の場合には人工弁に置き換える手術となります。人工弁はチタンでできており十分な耐久性がありますので、途中で壊れるのではないかという心配は全く無用です。
手術ではまず悪くなった自分の弁を切り取ります。すると弁が付いていた部分がリング状に残りますので(この部分を弁輪部といいます)、ここにピッタリの大きさの人工弁を置きます。人工弁はリング状の弁座の中で2枚の板状の弁が開閉する形のものが主流で、この弁座が布で覆われており、この布と弁輪部を糸で縫い合わせるのです。人工弁置換術の後は、人工弁に血栓が付かないようにワーファリンという名の血を固まりにくくする薬を服用する必要があります。
第3は動脈硬化が原因の虚血性心疾患に対するバイパス手術(CABG)です。狭心症と心筋梗塞のページでも少しふれましたが、最近ではカテーテルによる治療が普及したことで、手術の対象となるのはかなりの重症例になってきました。以前は下肢の内側にある大伏在静脈を摘出し、大動脈と冠状動脈の2カ所に吻合することで、狭窄部位をバイパスして血液を流していましたが、もともと低い静脈圧に対する構造である静脈を動脈の血圧がかかるバイパス血管として使用するには無理があるようで10年以内に閉塞してしまうことが多いことがわかってきました。
そこで、重要な部位へのバイパスとしては、心臓の近くを走行している内胸動脈をはがして、冠状動脈に縫いつける手術が主流となっています。この方法では、内胸動脈の根元はもともと動脈の枝別れですので、吻合するのは冠状動脈との1カ所で済みます。しかし、下肢の静脈に比べて細いので、縫い合わせるのは高度の技術が必要となります。内胸動脈は胸壁の裏側の左右に1本ずつあるので、2カ所の吻合に用いることができます。また内胸動脈は本来胸壁に血液を送る血管ですが、これをはがして心臓に吻合しても、胸壁には他の血管からも血液が供給されているので術後に虚血症状が見られることはほとんどありません。
この手術は心臓の内腔の手術ではなく、心臓表面にある冠状動脈の手術ですので、必ずしも心臓を止める必要はないのですが、吻合が細かいため、拍動しているとさらに難しくなります。しかし心筋保護で述べたように、心臓を止めることは心臓の機能を低下させることになるため、最近ではなるべく心臓を止めずに拍動下で吻合するようになってきております。これにより、かなり弱った心臓でもバイパス手術ができるようになってきました。
( 展 望 )
現在でも、心臓外科の領域は手術手技、心筋保護、体外循環の面で年々進歩し続けています。最近では、従来心臓移植でしか助ける方法がなかった拡張型心筋症に対して、バチスタ手術を積極的に行い成績を向上させている施設もあります。先天性心疾患ではより生後早期に、そして胎児での手術へと向かっており、手術成績は飛躍的に向上しています。心臓移植ではドナーの数は少ないながらも成績は良好で順調に行われています。人工心臓の分野では、機器の改良により、近い将来には体内への完全な埋め込みも一般的に行われるようになるでしょう。そして、今後も増加が見込まれる虚血性心疾患に対するバイパス手術では、ほとんどの場合で、体外循環、心停止を行わない手術が行われ、主流になってゆくでしょう。