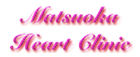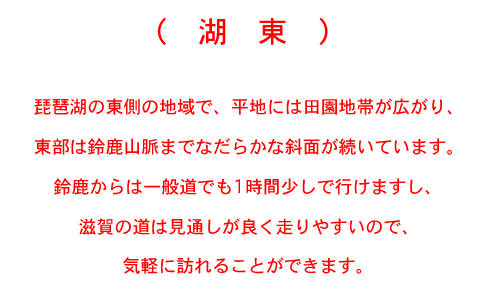(八幡山から見た安土山)
琵琶湖東岸の中央部に位置するのが安土です。織田信長にとって、尾張と京の中間地点である安土は、城を築くのにベストのポジションであったと思います。写真は西の湖の突き当たりに位置する安土山(189m)で、近江八幡の八幡山ロープウェイを上がり山頂から見たところです。安土城が置かれた安土山は琵琶湖とすぐ後ろの繖山(きぬがさやま、433m)に挟まれており、攻撃されにくいロケーションだと言えるでしょう。はるか向こうには鈴鹿山脈が望めます。

(西明寺の紅葉)
湖東といえば湖東三山、湖東三山といえば紅葉で有名ですが、寺院そのものも魅力的です。最も北に位置する西明寺は仏像のページでも紹介している三重塔の内部が必見です。真ん中に位置する金剛輪寺は階段の両側に並んだ多数のお地蔵さんと二天門にかけられた大きなわらじが印象的です。最も南の百済寺(ひゃくさいじ)は庭園もきれいです。これらの寺院は山の斜面にあり大きいので、山門から本堂まで登って行くのは結構疲れます。

(五個荘)
五個荘(ごかしょう)は安土のすぐ西側の町で、近江商人発祥の地、てんびんの里とされています。観光客が少なく駐車場も無料ですので、ゆっくり歩くには最適の場所です。国の重要伝統的建造物として保存された白壁の近江商人屋敷、多くの錦鯉が泳ぐ町中の水路、きれいな町並みを見ながら歩けます。

(石馬寺)
五個荘の奥にある石馬寺(いしばじ)は繖山の西側斜面で安土山とは反対側に位置します。聖徳太子がこの地を訪れた際に乗ってきた馬が石と化したため、石馬寺と名付けたとされています。石段を登って行くと閑静なお寺が現れます。写真は石馬の石庭とよばれている庭園で寺の縁起を表しているそうです。他には誰もいなかったのですが大佛宝殿を開けていただきました。そこは重要文化財の宝庫で至近距離でゆっくりと多くの仏像を拝むことができ充実したひとときを過ごせました。

(草津市立水生植物公園みずの森)
県立琵琶湖博物館とともに琵琶湖東岸の烏丸半島にあるお勧めの施設です。まず博物館内にある淡水魚の水族館を見学します。最近では少し色がうすくなってしまった金色の大ナマズや中国の大きな川魚など他では見たことのないような魚達が見れます。 チョウザメの餌付けもおもしろいです。 その後、大きな風力発電機のくさつ夢風車の真下に移動し、水生植物公園に入ります。いろいろな色の花が咲いたスイレンやオニバスがとてもきれいで楽しめます。

(烏丸半島ハス群生地)
水生植物公園のすぐ裏手に広がるハスの群生地で、7月下旬から8月上旬が見頃だそうです。淡いピンクの大きな花が一面に咲いています。真夏にきれいな花が見たくなったら、ここがお勧めです。むこうに見えるのは近江富士(三上山、432m)です。

(永源寺の紅葉)
永源寺の紅葉が美しいと聞いて初めて行った時のことは忘れられません。最短ルートを地図で見ると、菰野から国道421号線を行けば近いとわかりいざ出発。 国道には八風街道となかなか良いネーミングの表示。だんだんと山の中に入ってゆき、頂上に近づいた時です。突然道幅が極端に狭くなり、なんと大きなコンクリートブロックの門があるではないですか。それも間隔は約2m。なんじゃこりゃー、頭の中は真っ白。車は半年前に買い替えたばかり。引き返そうかとも思いましたが、前方からワンボックスカーが来たので絶対に通れるはずだと信じ、サイドミラーをたたみ、運転席の窓を開けて超低速で侵入、車体ぎりぎりで通過しました。山頂の道は狭くて車1台分、路肩が崩れそうで怖かったです。対向車のゆずり合い精神に助けられ、県境の石榑峠にさしかかると、再び同じコンクリートブロックの門。今度は引き返そうにもスペースはなく、勇気を出してなんとか無事に通過しました。そこから永源寺までは川沿いのなだらかな下り坂できれいな紅葉が続いていました。もちろん帰りは国道1号線に回りました。もう二度と石榑峠を越えることはないでしょうが、鮮烈な思い出です。