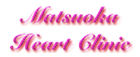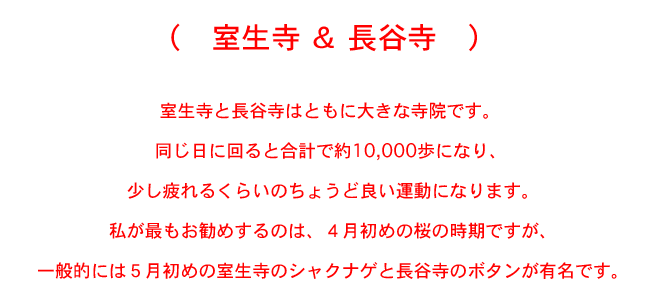(室生寺 正面)
太鼓橋から見た正面の風景です。橋のたもとの橋本屋のテーブルでいただく精進料理はどれも味がしっかりしていてなかなかおいしいです。
女人禁制の高野山に対して、室生寺は女性の参詣を許していたことから女人高野と呼ばれるそうです。しかし五重塔から奥の院までは階段が急で、女性がそこまで行くのはかなりしんどいと思います。
室生寺は国宝の宝庫です。特に五重塔と金堂ははずせません。そして金堂内に並ぶ仏像も見事な国宝です。中央には一木作りの御本尊の釈迦如来立像(お顔は少しかがまないと見えません)、一番左には超有名で色彩豊かな十一面観音像があり、シーズンオフにはゆっくりと拝めます。

(五重塔から見下ろした風景)
室生寺の桜は、なんと言っても大きいのが特徴です.
五重塔から見下ろすと、桜の木は本堂の屋根よりも高い枝にまで花をつけていました。

(室生寺五重塔)
本堂の方から五重塔を見上げたところです。4月末には階段の両側にはシャクナゲが満開でした。
法隆寺の重厚感のある五重塔とはまたちがい、室生寺のは下から見上げた時にとても美しい五重塔です。

(室生寺のシャクナゲ)
室生寺のシャクナゲは、さすがに1株が大きく、花数が多いです。
シャクナゲは鹿沼土のように水はけがよく、半日陰の所によく育つとのことですが、室生寺のシャクナゲも半日陰の斜面によく育っておりました。

(花の郷 滝谷)
室生寺の近くにある、 花の郷 滝谷の一番奥にあるはなずおうの木です。満開でした。
この木に比べると小さいですが、室生寺の五重塔の周辺のはなずおうもきれいでした。
ここも園内はかなり広いので、健康お散歩コースです。ただし入園料はやや高い感じがしました。

(長谷寺 正面)
駐車場から歩いて行くと、道の両側にいろいろなお店が並んでいます。三輪ソーメン、吉野葛、草餅、奈良の漬け物など、ご当地ならではの食材があふれかえっていました。
長谷寺の正面に立つと、入り口から山の斜面にまで満開の非常に美しい桜が出迎えてくれます。これほどきれいな景色はめったに見られないでしょう。

(しだれ桜と仁王門)
春の訪れとともに長谷寺のしだれ桜がまず開花し、非常に美しい純白のモクレンとともに満開になります。
正面の仁王門から登廊が続きます。桜が満開の時期には、登りきった所の本堂やその奥の五重塔が、山の斜面を埋めつくした桜の中にまるで浮かんでいるように見えます。

(登廊右側に咲き誇るボタン)
ボタンの花はようやく満開になったと思うとすぐに散り始めるのがちょっと残念な気がします。
長谷寺本堂まで登ると(特に室生寺の奥の院まで参った後の場合)、かなり下肢に疲労を感じます。しかし、登廊を上がりきった所の自動販売機でのどを潤した後に本堂の中に入ると、御本尊の前でその疲れは吹っ飛びます。

(美しい長谷寺のボタン)
数ある十一面観音像の中で、私が最も好きなのが、この長谷寺の御本尊の十一面観世音菩薩立像です。本堂の中に安置され、御身の丈は約10mで金色に輝き、見上げるとその美しさに圧倒されます。
写真は本坊前で見つけたとても美しいボタンです。長谷寺のたくさんのボタンの中でもこのような模様の花はこの1株しか見かけませんでした。

(長谷寺の紅葉)
さすがに花の御寺と言われるだけあって、いつ訪れても長谷寺を彩る花の美しさには見とれてしまいます。
これは11月末の風景で、本堂の舞台から五重塔の方向を見たところです。とても鮮やかな紅葉で感動しました。
偶然このとき、長谷寺大観音特別拝観が開催されており、なんと私の大好きな十一面観世音菩薩立像の御足に初めて触れることができました。昔から参拝者がご縁を結ぶためになでるため、御足は黒光りしておりました。真下から見上げた観音様は本当に頼もしく感じられ、頭上中央正面には立像を冠しておられるのに気づきました。さすがに他の十一面観音像とはちょっと違うようです。
飛鳥時代から続くこんなに美しい寺院を鈴鹿からはいつでも日帰りで気軽に訪れることができます。本当に嬉しく思います。