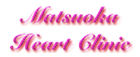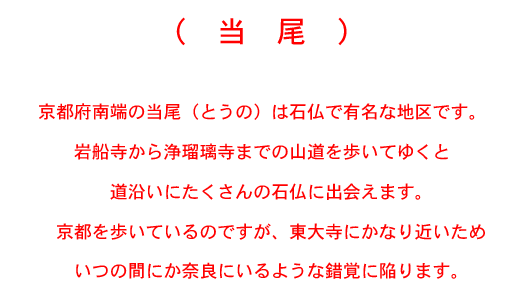(岩船寺)
アジサイの名所として知られる静かで風情のあるお寺です。聖武天皇により天平時代に建立されました。すぐ前の駐車場から階段を数段上って門をくぐると、三重塔や十三重石塔が見えてきます。三重塔は室町時代に建てられたものですが、平成15年の大修理により朱色が鮮やによみがえり、現在ではとてもきれいになっています。

(三重塔から見た本堂)
十三重石塔は鎌倉時代のもので、重要文化財に指定されています。 本堂には御本尊の阿弥陀如来坐像、四天王像などが安置され、かなり近くでゆっくりと見ることができます。象の上に乗っている普賢菩薩騎象像もユニークな仏像です。中心の池を囲むように塔や本堂が配置されており、浄瑠璃寺と共通するところです。

(当尾の山道)
岩船寺の門の前では地元でとれた農作物や焼き芋、草餅などが売られており、周辺では無人販売所も多く見られます。歩いて浄瑠璃寺に向かうと、散策路はこのような山道になります。写真の右側は谷ですが、設置された階段を降りてゆくと石仏があったりします。

(笑い仏)
山道を少し進むとまず当尾で最もよく知られた石仏である笑い仏に出会えます。大きな岩にくっきりと彫られた阿弥陀如来が両側の観音菩薩と勢至菩薩とともに微笑んでおられます。

(薮の中三尊)
さらに歩いて行くと、カラスの壺や愛宕灯篭といった石造物が道標のように置かれており、 薮の中三尊に到ります。写真のように向かって右から十一面観音菩薩立像、地蔵菩薩立像、阿弥陀如来坐像が彫られています。鎌倉時代の作で当尾の石仏の中では最古のもののひとつだそうです。

(大門の仏谷)
薮の中三尊まで来ると浄瑠璃寺は近いですが、あえて脇道に入り、首切地蔵、大門石像群などを見ながら進むと大門の仏谷に到ります。谷の向こうに見えるのが当尾で最大の石仏で、高さ6mの岩に彫られた大きな磨崖仏です。なかなか立派なものです。そこから引き返して浄瑠璃寺に到着し、いつも門前にある食堂「あ志び乃店」で昼食です。山菜とろろそばがおいしくて毎回楽しみです。

(浄瑠璃寺本堂)
浄瑠璃寺は本堂も三重塔も国宝で平安時代のものです。初めて訪れた時は本堂の中にずらりと並んでおられる金色の九体阿弥陀如来像の荘厳さにびっくりしました。また普段は厨子に入っておられる秘仏吉祥天女像ですが、春と秋と正月に公開されているので会えることが多くて嬉しいです。出口近くの不動明王三尊像も鎌倉時代の作で素晴らしく、右側の矜羯羅童子はとてもかわいいです。

(宝池と三重塔)
本堂から三重塔を見ると景色がきれいです。池のまわりをぐるっと回って三重塔に着きます。藤原時代の秘仏薬師如来像が安置されており、毎月8日の好天時には拝むことができます。浄瑠璃寺を後にして門前の骨董屋などを見てから来た山道を岩船寺の方へ戻りますが、帰りが登り坂となりますのでかなり疲れます。この当尾の散策コースはアップダウンがありますので少ししんどいですが、充実感が得られますのでぜひ訪れてみて下さい。