(第37回)
![]()
![]()
(第37回)
用語とありますが、言葉だけにこだわらずに、ルール面など剣道に関するクイズをしていく予定です。子どもたちやおうちの方々、剣道をあまり知らない方がちょっと詳しくなれるといいなぁ、と思っています。
このページも文責はToshiです(Toshiの知識および調べた範囲内ですので、解答に間違いなど有りましたら、ご指摘ください)。
(第38問)(久しぶりに初心者問題)
竹刀を帯刀したとき、竹刀の弦(つる)はどちらを向いているのが正しいでしょうか。
(1)上
(2)下
(3)特に決まっていない
(第37問)
剣道における「最高位」とは、何でしょうか。
(1)八段
(2)範士
(3)皆伝
(第36問)
有効打突の条件は、「充実した気勢、適正な姿勢をもって、竹刀の打突部で打突部位を刃筋正しく打突し、残心あるもの」(剣道試合審判規則第12条)ですが、さて、この「刃筋正しく」とは、どのようなことでしょう。
(1)床に対して垂直に振り下ろして打突すること。
(2)打突の方向と刃部の向きが同じ方向であること。
(3)竹刀の振り上げと振り下ろしが同じ軌跡を描くこと。
| (第35問) 今回はかなり毛色の違う問題ですが… 剣道関係者がよく付けているこのバッチ。全剣連の徽章なのですが、さてこの名前は? (1)剣道審判員バッチ (2)剣道指導員バッチ (3)剣道人バッチ |
 |
(第34問)
審判員が主審・副審を交代する場合、移動中に旗をどのように持つでしょうか?
(1)直前に持っていたまま、両手にそれぞれの旗を持って移動する。
(2)右手に2本まとめて持ち、移動する。
(3)左手に2本まとめて持ち、移動する。
(第33問)初級問題
自分の試合の前に、審判が交代することとなりました。その時、自分はどの位置にいることが正しいでしょうか。
(1)試合場(コート)の外で待つ
(2)試合場内の立礼の場所(開始線三歩手前)で待つ
(3)礼をした後、開始線で蹲踞して待つ
(第32問)今回は、ちょっと趣向を変えて。
| 団体戦で、大将戦になりました。大将Aくんは、一本勝ちしてきた副将と握手し、コートに入ると、審判に一礼。続いて、相手に礼をして三歩進んでそんきょ。主審の合図で試合が始まりました。 試合は、決め手がないまま進み、残り1分となりました。興奮した次鋒のBくんは、あぐらをかいたヒザを叩いて、「いけ!がんばれ!」と叫びました。更に試合は進み、腕時計を見て監督は「あと30秒!」と声をかけ、かねてから決めてあったサインをAくんに送りました。Aくんはサイン通りに抜き胴を決め、そのまま試合終了となりました。 |
さて、上の試合描写には、剣道において「してはいけないこと」「しない方が望ましいこと」が複数あります。どれか、わかりますか?
(第31問)
団体戦で不戦勝となった場合は、どのように不戦勝ちの宣告を受けるでしょうか。
(1)チーム全員が団体戦の礼の位置に整列し、主審の宣告を受ける。
(2)先鋒から大将まで、順番に個人戦の時と同様に不戦勝ちの宣告を受ける。
(3)大将が代表して、個人戦の時と同様に不戦勝ちの宣告を受ける。
(第30問)
今回は審判に関する問題です。
A選手が面を打ったところ、副審の一人が有効打突と判断して旗を上げ、主審は無効と判断して旗を振りました。もう一人の副審は、判定を棄権しました。
さて、この場合、判定はどうなるでしょうか
(1)判定は主審が優先されるため、一本となる。
(2)判定が分かれたため、合議をして判断する。
(3)「有効打突」と判定した人数が2人に満たないため、無効となる。
(第29問)
面から体当たりをされたA選手が、場外に出てしまいました。審判が「止め」をかける前に体当たりをしたB選手の方も勢い余って場外に出てしまいました。さて、この場合反則になるのは誰でしょう。
(1)先に場外に出たA選手のみ
(2)A選手B選手の両方が反則になる。
(3)後から場外に出たB選手のみ
(第28問)
A選手が、B選手に対して小手を打ちました。裏側に回っていた審判二人が「一本」と判定し旗を上げましたが、一番よく見える位置にいたと思われる審判Cが、激しく旗を振って否定しました。この場合、主審はどうするべきでしょうか。
(1)審判Cが一番よく見えていたはずなのだから、その意見を採り上げ、一本を取り消す
(2)審判二人が有効の判定をしたのだから「一本」
(3)合議をかけ、選手を下がらせて検討する。
(第27問)
個人戦で、両方の選手が1回ずつ場外に出て、それぞれに反則1回がカウントされました。その後、延長になってから、片方の選手が再び場外に出て反則をとられました。
この場合、どうなるでしょうか。
(1)この試合で2回目の反則となるので、相手に一本で負け。
(2)延長は、延長のみで反則がカウントされるため、「反則1回」で続行。
(3)延長でのみ反則がカウントされ、「反則1回」となり、ポイントがリードしたため、相手の勝ち。
(第26問)
試合中に、竹刀が真っ二つに折れてしまいました。
さて、この場合どうなるでしょう。
(1)「刀を折られた」ため、相手に2本を与えて負け。
(2)審判員の指示でいったん下がった後、竹刀を交換して再開。特にペナルティーはなし。
(3)竹刀は交換できるが、反則1回
(第25問)
審判は、交代の際に旗を巻きますが、赤白どちらが外になるように巻くでしょうか。
(1)赤が外側
(2)白が外側
(3)特に決められていない。
![]()
|
(第23問)
試合中に怪我をした場合のことで、正しいのはどれでしょう。
(1)審判は選手が納得しなければ、試合を打ち切れない。
(2)団体戦で負傷棄権すると、その後の試合には出場できない。
(3)基本的に試合続行の判断は審判が五分以内にしないといけない。
(第22問)
剣道の大会は、必ず3本勝負で行われなければならないでしょうか。
(1)もちろん、そのとおり。
(2)運営上必要であれば、1本勝負としてもよい。
(3)1~5本の任意の本数勝負を審判長の権限で設定する。
(第21問)
試合開始時の副審の立ち位置はどちらが正しいでしょうか。
(第20問)
今回は、審判員の服装について。
紺のブレザー、灰色のスラックス、白のワイシャツ、えんじのネクタイと決まっているのは見ていてよく判ると思いますが、さて、靴下は何色?
(第19問)
試合をするコートについての問題です。
試合場の辺の長さは、9~11mの四角形と決まっていますが、さて、形はどうでしょうか。
(1) 長方形でもよい。
(2) 正方形しかいけない。
(3) とにかく、四角形であればよい。
(第18問)
今回は、初級問題。
面には、中央に縦金、そして横金がついています。
この横金と横金の間は、どうなっているでしょうか。
(1) すべて同じ幅である。
(2) 違う幅のところもある。
さぁ、面を見て確認してみましょう(笑)
![]()
(第17問)
「小手」に関する問題。
中段の構えの場合、「小手」が一本になるのは、相手の右小手を有効打突の条件を満たして打った場合です。
では、もし中段の構えで、相手が左手を前にして構えた場合はどうなるでしょうか。
(1)右小手が一本の対象となる。
(2)左小手が一本の対象となる。
(3)そんな構えは認められないので、それ以前に審判に注意される。
(第16問)
A選手は、試合でまず小手を先取しました。試合再開後、体勢を崩して立て直そうとしたときに左足をひねり、アキレス腱を切ってしまい、試合の続行が不可能になりました。特に対戦相手のB選手には、故意・過失が認められませんでした。
さて、この場合、試合結果(取得本数)はどうなるでしょう。
(1)1-0でA選手の勝ち(試合中断時点までで判断される)
(2)1-0でB選手の勝ち(試合不能で、相手に一本、A選手の一本は取り消し)
(3)2-0でB選手の勝ち(試合不能で、相手に二本、A選手の一本は取り消し)
(4)2-1でB選手の勝ち(試合不能で、相手に二本だが、A選手の一本も認められる)
(第15問)
二刀を使う場合、大刀の長さはどのように決められているでしょうか。
(1)114センチメートル(三尺七寸)以内
(2)117センチメートル(三尺八寸)以内
(3)120センチメートル(三尺九寸)以内
ちなみに、一刀の場合、通常大学生一般では、120センチメートル以内です。
![]()
(第14問) 今回は、2択で。
高校生以上から有効打突と認められる「突き」ですが、これは、面の突垂以外に胴の胸の部分もついてよいでしょうか。
(1)胸の部分も一本になる。
(2)胸の部分は一本にならない。
![]()
(第12問)
剣道で「放心」とは、どういう心の状態をいうでしょうか。
(1)全力を使い果たして、ぼうっとしている隙の多い状態
(2)臍下丹田に溜めた気力を相手に対して、一気に解き放つ状態
(3)一つのことにとらわれずに、どんな変化にも対応できるような状態
![]()
(第9問)
竹刀を分解してみると、柄がしらの中に四角い金属の板が入っています。
さて、ズバリこの名前は?
(1)ちぎりがね
(2)むすびがね
(3)あわせがね
![]()
たまには、簡単な問題を。
(第8問)
試合で、時計係は旗を持っています。これは何色でしょうか。
(1)白
(2)緑
(3)黄
![]()
(1)50センチメートル。
(2)70センチメートル。
(3)100センチメートル。
![]()
第2回は、反則について。場外反則のことをクイズとします。
(第2問)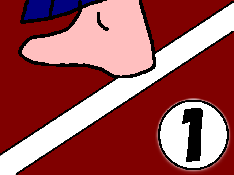 |
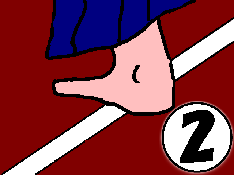 |
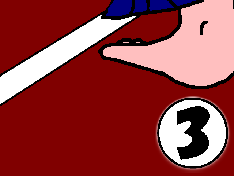 |
| 片足が少しでも 境界線を少しでもふんだとき |
片足の一部分が 境界線の外に出たとき |
片足が完全に 境界線の外に出たとき |
(第1問)
次の( )に当てはまるのは、どの言葉でしょうか
剣道は剣の理法の修錬による( )形成の道である
(財)全日本剣道連盟 昭和50年3月20日制定「剣道の理念」
Copyright (C) 白剣会スポーツ少年団 2002-2003 All rights reserved.